 🔰リーダー里美さん
🔰リーダー里美さん部下が指示を待ってばかりで動かない…です。
どのように指示をだしたら自発的に動くか教えてください。



リーダーの関わり方次第で、部下が積極的に行動するチームへと変わりますよ。
本記事では、「なぜ部下が指示を待ってしまうのか?」という3つの原因をひもときながら、部下のやる気を引き出す3つの手順を紹介します。
結論から言えば、
- まずは質問する
- 小さな決定をまかせる
- 行動を具体的にほめる
この順番で関われば、指示待ちだった部下も自分から動くようになります。
私はクレームが多かった部署を2年でゼロにし、5年間で約300人の後輩を育ててきた女性リーダー歴10年以上のユリです。
現場で効果があった方法だけを厳選してお届けするので、やってみればすぐに変化が見えるはず!
読み終える頃には…
- 「指示」より「質問」で声をかけられる
- 部下の行動量がぐんと増える
- 少しずつ仕事を任せるコツがわかり、自分の残業時間も減るでしょう!



チームみんなで
「共有→挑戦→ほめ合い」
のサイクルを回して、成果も雰囲気も一緒に良くしていきましょう!
悩みの正体:なぜ部下は指示を待つのか?
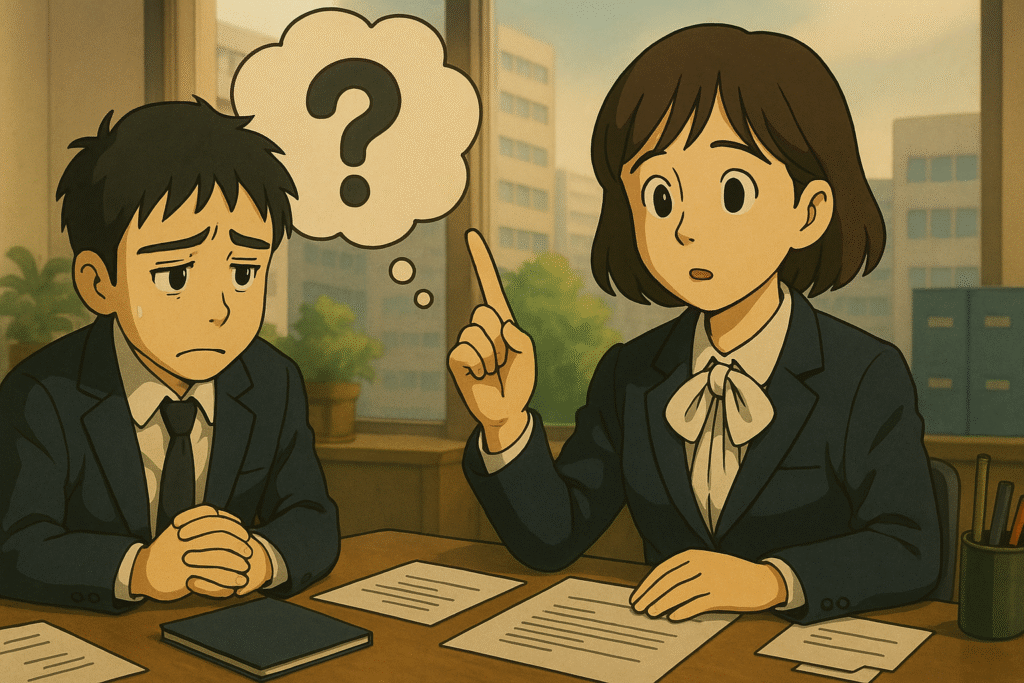
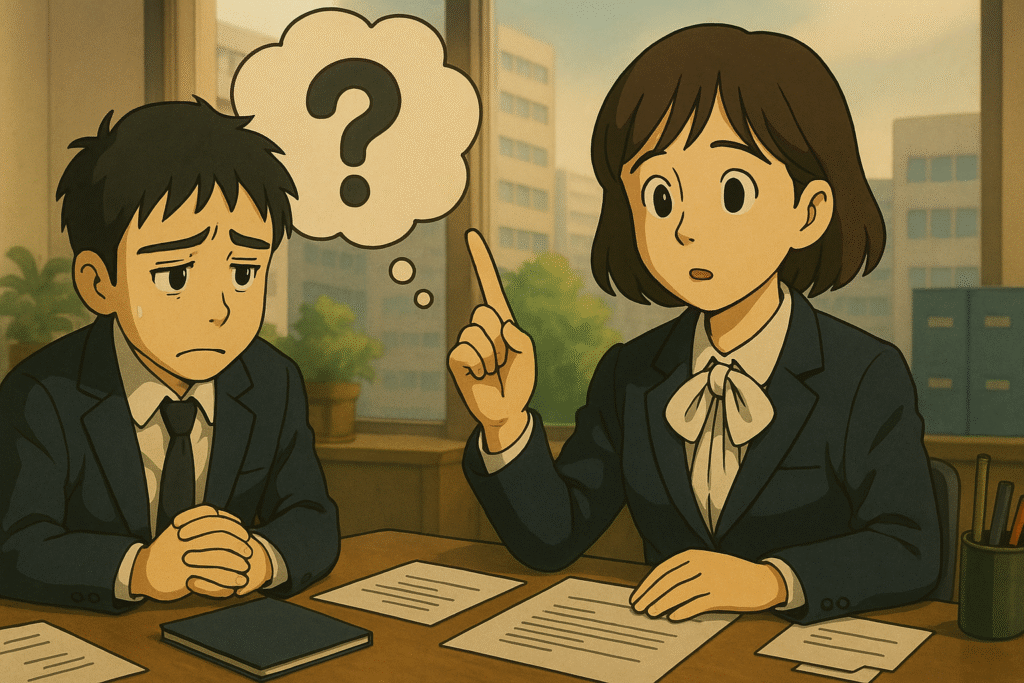
部下が「指示がないと動けない」状態に陥る背景には、さまざまな要因が存在します。
ここでは、指示待ち部下が生まれる主な原因と、それに対する具体的な対応策を3つ紹介します。



原因を知ることで、部下の主体性を引き出し、チーム全体のパフォーマンスをあげられました!
原因①:目標や役割が曖昧
部下が動けないときは、目標や自分の役割が曖昧になっている可能性がある。
「何をすればいいのか」が明確でないと、行動に移すことができず指示待ちに。
動きが鈍い部下がいたら、まず個別に目標を確認し、
「目標達成のために、あなたは何ができると思う?」
と問いかけてみましょう。



スムーズに答えが出れば理解している証拠、わからない様子なら、納得できるまで丁寧に教えてあげましょう。
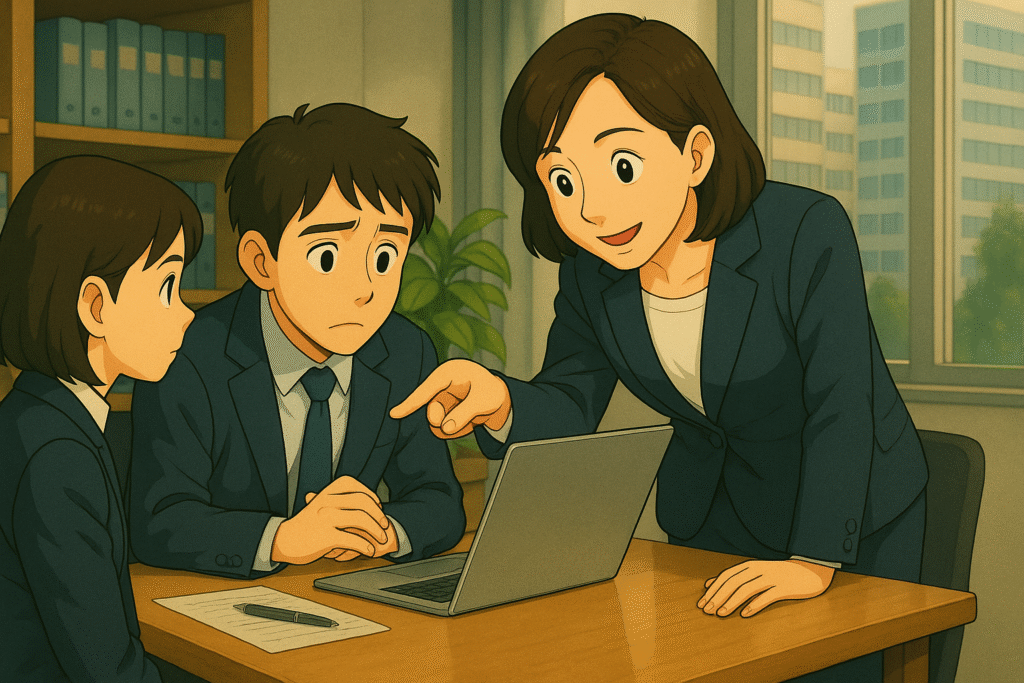
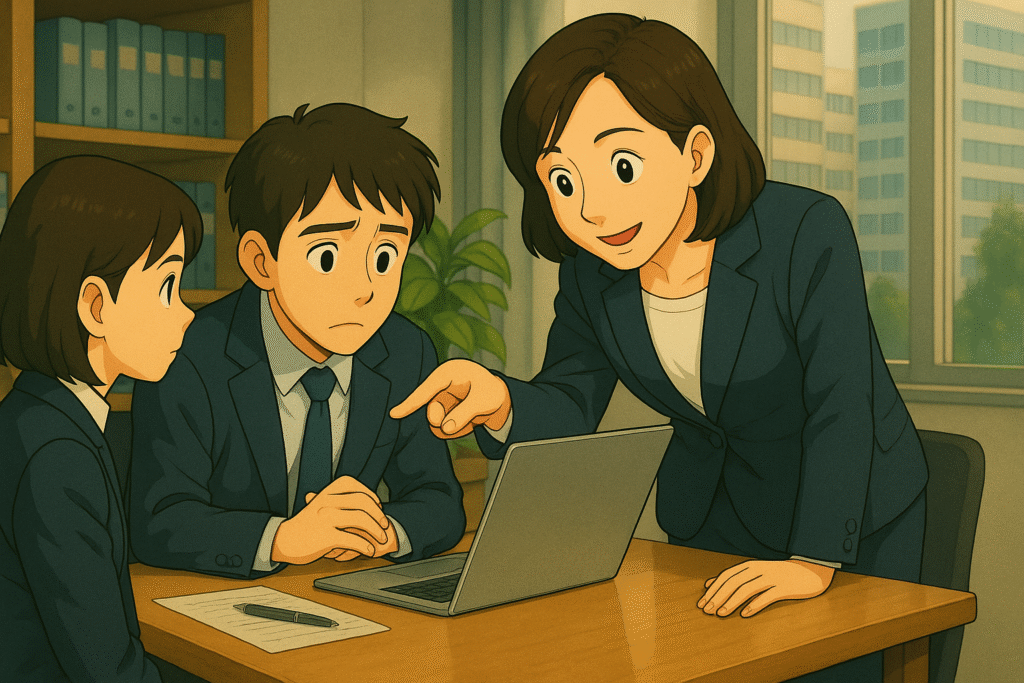
原因② :失敗への恐怖心
部下が慎重になりすぎて動けないのは、失敗への恐れが強い可能性がある。
誰でも失敗は怖いものですが、過度に恐れると、チャレンジする意欲そのものが萎縮してしまいがち。
そんなときは、
「失敗しても大丈夫だよ!」
とリーダーが背中を押し、安心してチャレンジできる雰囲気をつくりましょう。



失敗したくないと思うのは当たり前。
その気持ちを理解してあげましょうね!
原因③ :過去の経験が影響している
部下が自発的に動かないのは、過去のネガティブな経験が影響している可能性がある。
以前に「考えて動いたら怒られた」という体験があると、「考えるより指示を待とう」と思ってしまいがち。
リーダーは、部下が自主的に動いた行動をしっかり評価し、小さな成功体験を積み重ねさせることが大切。



少しずつ自信が育てば、自然と自発的な行動も増えていきます。




STEP1|考えさせる質問で「思考のスイッチ」を入れる
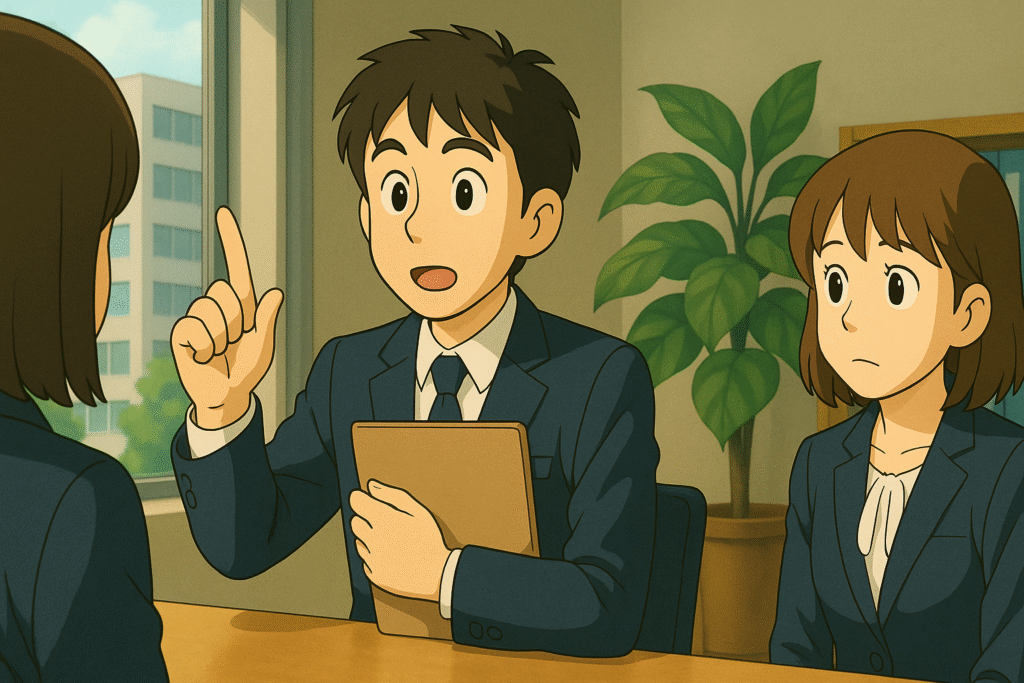
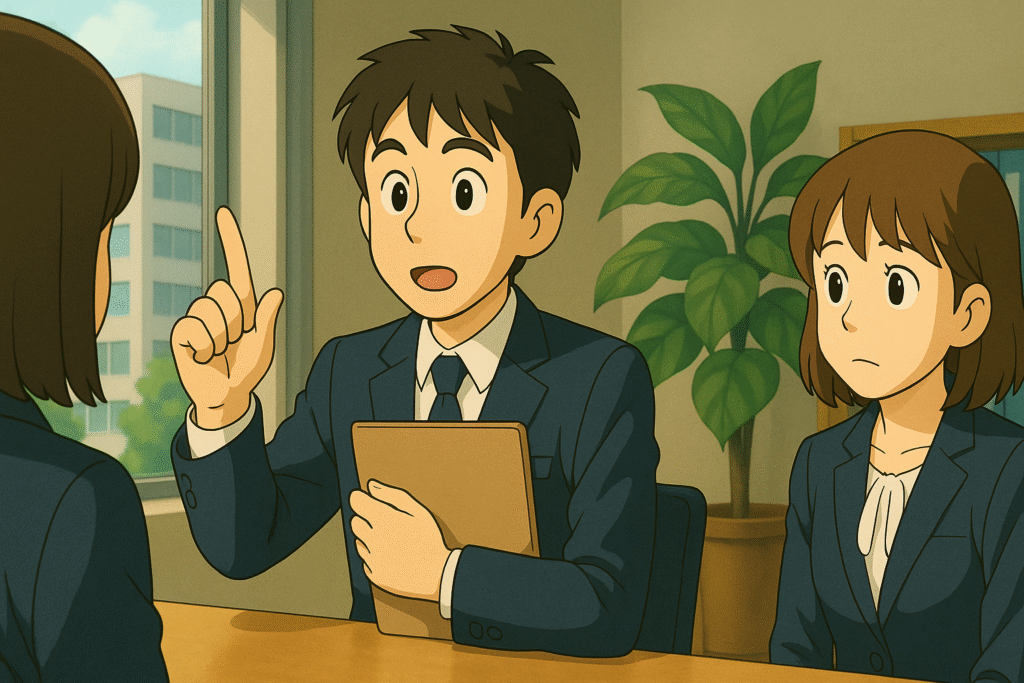
部下が自発的に動くためには、リーダーの関わり方が大きく影響します。



指示を出すだけではなく、部下が自ら考え、行動するよう促す工夫が求められます。
即答禁止!まずは「君はどう思う?」
部下の自発性を育てるには、「自分で考える」習慣を促す関わりが効果的。
リーダーがすぐに答えを与えるのではなく、部下に考える機会を提供することで、思考力と自信が育まれます。
例えば、
– 君はどう思いますか?
– 解決策を3つ考えてみて
の問いかけを行うことで、部下は自ら考える力を養い、自信を持って行動できるように!



質問されたらすぐ答えるのではなく、考える習慣をつける質問を投げかけてあげてね。
STEP2|小さな決定権を渡し“当事者意識”を育てる
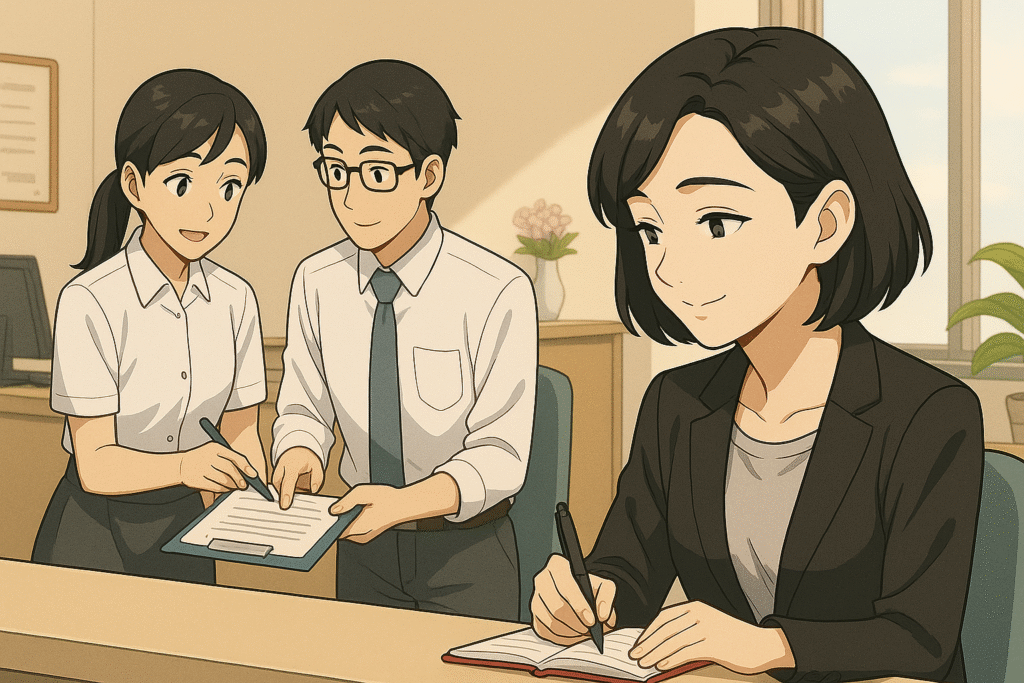
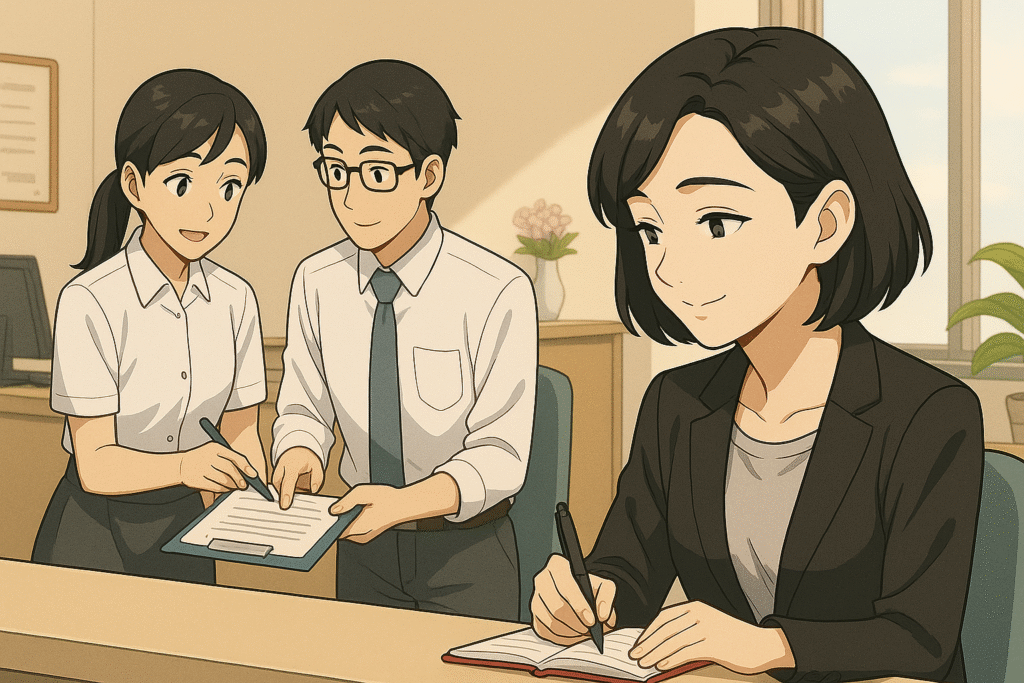
小さな 「選ぶ・決める」を部下に任せると、仕事を「自分ごと」と感じ、やる気と行動スピードが上がる。
タスクの全体像がわかったら、次は
– どちらを選ぶ?
– 進め方は任せるね
など小さな意思決定を部下に委ねましょう。
次第に責任感と主体性が芽生えます。



自分で選び結果を背負う経験を重ねると、当事者意識が高まり、指示を待たずに動けるようになりました。
実践ヒント
| 任せ方 | 具体例 | セーフティネット |
|---|---|---|
| ミニ決定を選ばせる | 「AとB、どちらの提案で進めたい?」 | 「迷ったら5分でいいから相談しよう」 |
| 役割を肩書きで渡す | 「次の社内MTG、議事録リーダーをお願い」 | テンプレや過去資料を共有しておく |
| 小さなプロジェクトを委ねる | 「このタスクはあなたに一任するね」 | 進捗レビュー日をあらかじめ設定 |
- 最初は「選択肢を2つ」与える程度でOK。
- 決定後は口を挟まず見守り、つまずきそうならサポートする。
- 成功・失敗どちらでも「決めたこと」に対してフィードバックを行う。



「全部を任せる」のではなく「少しずつ任せて成功体験を積ませる」
これが自走する人材を育てる最短ルートでした。
STEP3|行動を“事実+具体”で褒め、成長を可視化する
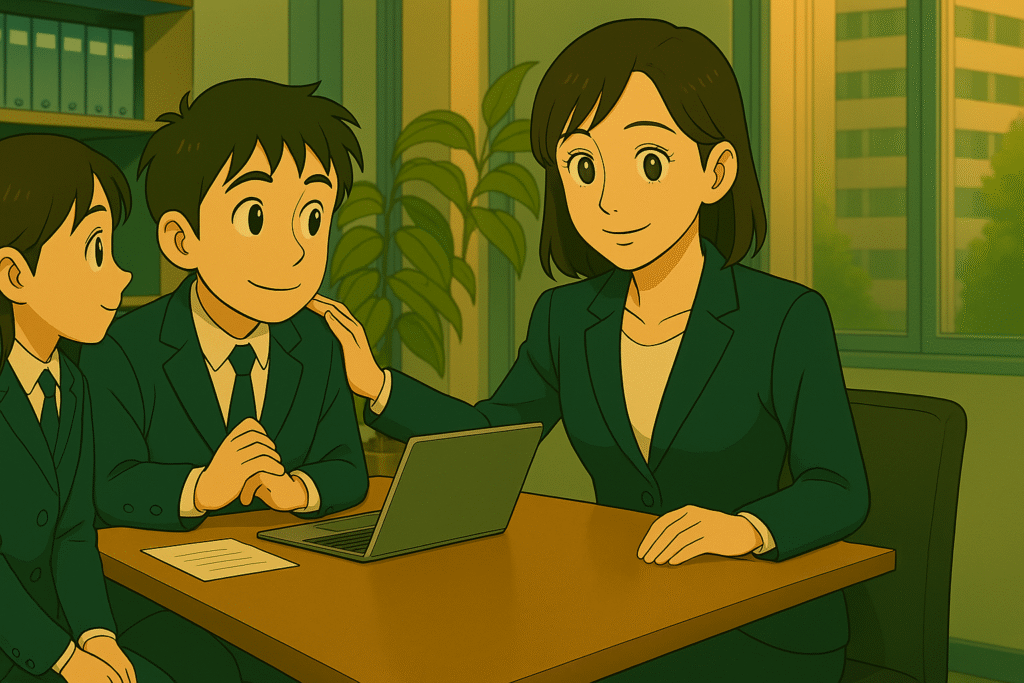
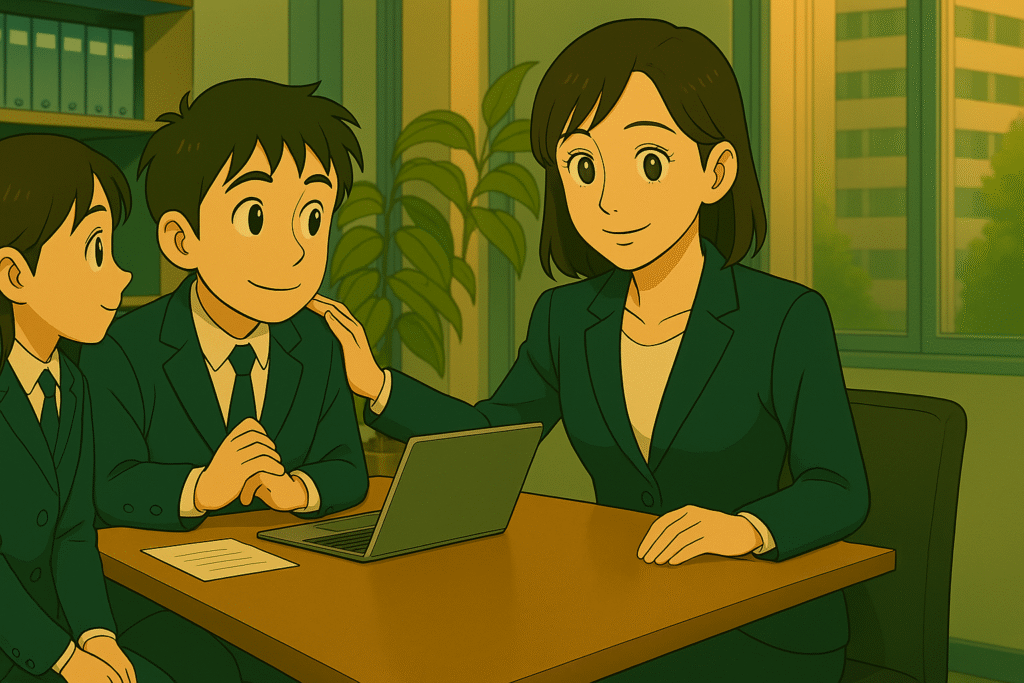
部下の行動を具体的に評価することで、自信とモチベーションが向上する。
行動を認められると、部下は自分の努力が評価されていると感じ、さらなる成長意欲が湧きます。
例えば、
-「チャレンジしたこと自体が凄いこと!」
-「この工夫、すごく良かったよ!」
と具体的に伝えることで、部下は前向きな気持ちで次の行動に取り組むようになります。
これらのアプローチを実践することで、部下の自発性を高め、チーム全体の成長を促進することができます。



どんなに失敗があっても、まずはチャレンジしたことを評価し、小さな良い点を伝えましょう。
自走チームを加速させる3つの仕組み
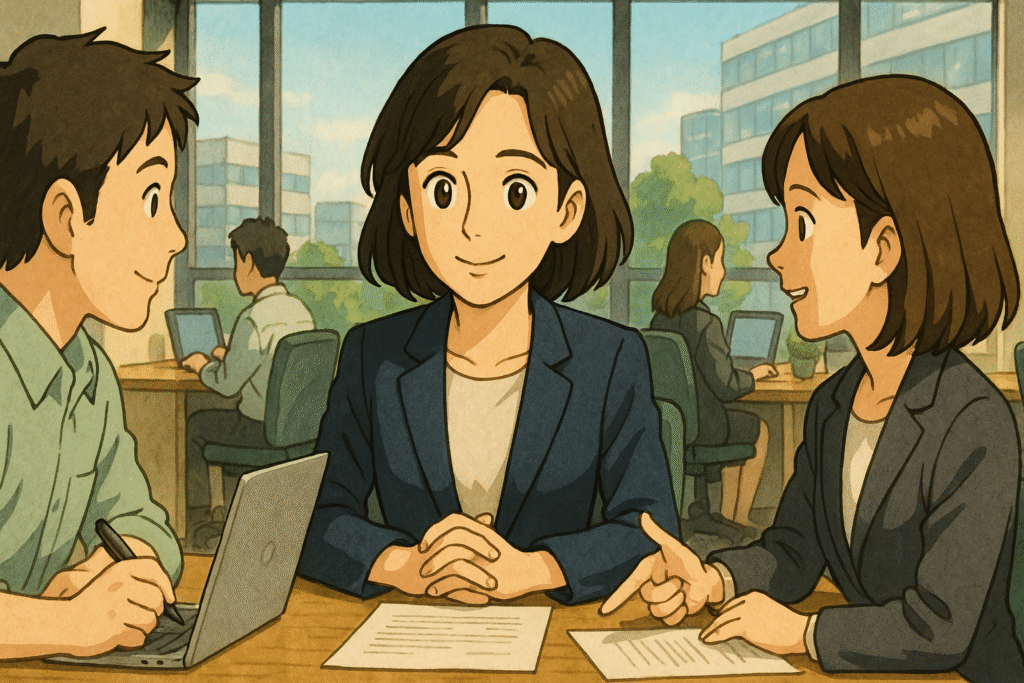
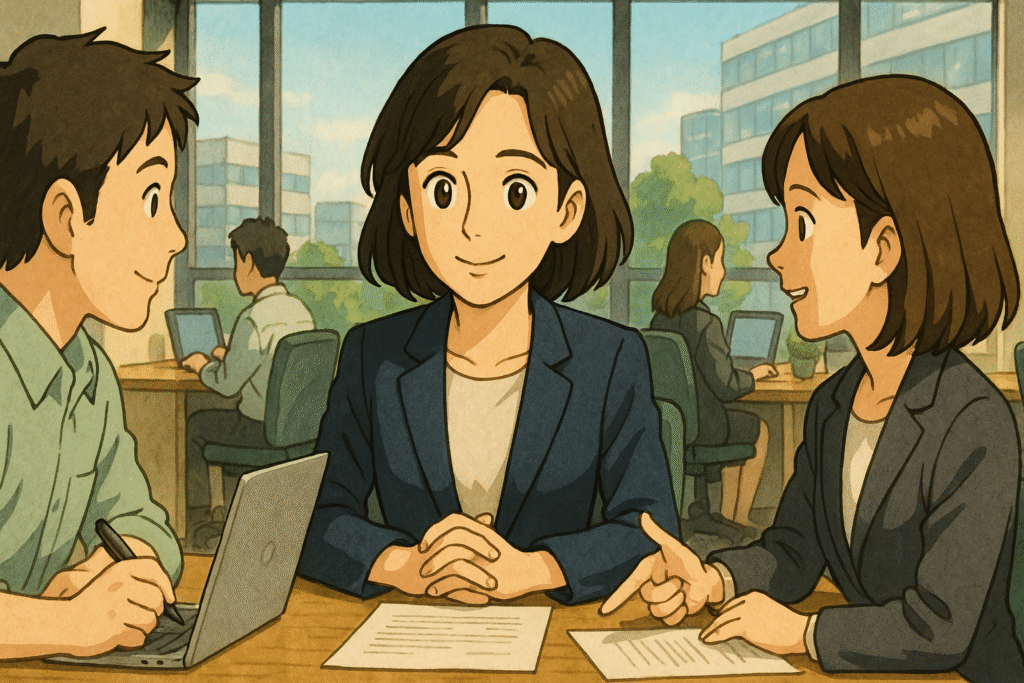
自分で考え、自分で動き、互いに助け合えるチームができると、リーダーが細かく指示を出さなくても仕事は回り、成果も加速度的に伸びていく。
ここからは、その土台をつくる3つのアプローチを紹介します。
アプローチ①:考えをシェアする場を作りましょう
「成功した工夫やうまくいかなかった失敗」をみんなで共有する時間をつくる。



成功例・工夫・失敗談をチームで気軽に共有するミーティングを定期的に開くと、メンバー同士が学び合い、モチベーションが上がりました。
共有された知識を聞いたメンバーは
「すごい!自分もやってみよう」
と感じ、以下のような好循環が起こります。
- 成功者への尊敬が生まれる → 真似して学ぶ
- 学んだことをすぐ試す → 行動が増える
実践ヒント
| やること | 具体例 | コツ |
|---|---|---|
| 週1回・5分の共有タイム | 「今週うまくいった工夫」 「失敗して学んだこと」 を各自1つ発表 | タイマーを使い1人1分で回す |
| 発表者をローテーション | 毎週順番を変え、全員が話す機会をもつ | 上司も失敗談を話して安心感をつくる |



シェアの場を仕組みにしてしまえば、知識とやる気が自然に循環し、チーム全体の底上げにつながります。
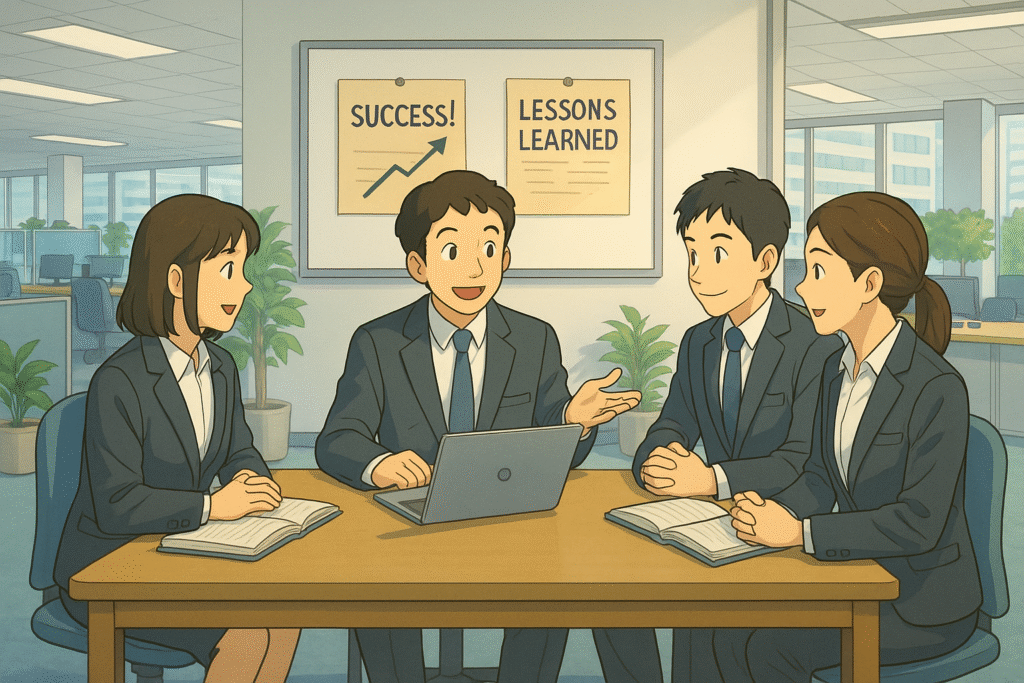
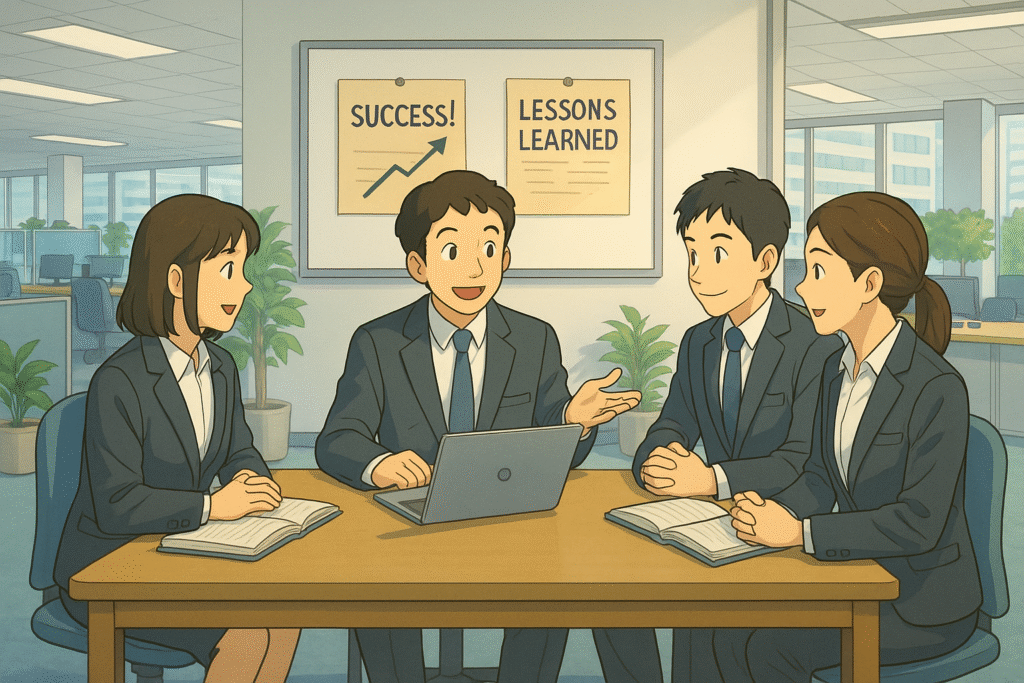
アプローチ②:責任感を持たせる役割設定をしてあげる
「今回の〇〇は君に任せるね」と小さな役割を渡すと、部下は責任感をもち主体的に動くようになる。



仕事を任されると「自分がやらなきゃ」と、当事者意識が芽生え、行動が積極的になります。
例(どう渡す?)
| 役割の渡し方 | 上司のひと言 | 効果 |
|---|---|---|
| 「議事録リーダー」 | 「次の会議、要点をまとめる係をお願い!」 | 会議の流れを主体的に考える |
| 「提案資料責任者」 | 「この提案書は君の最終チェックでOKを出してね」 | 資料の質を自分ごととして高める |
| 「プロジェクト進行係」 | 「今回はスケジュール管理をすべて任せるよ」 | 進捗を自分で組み立てる習慣がつく |
- まずは、「肩書き+1つのタスク」程度の小さな範囲から。
- 任せた後は口を出しすぎず、困ったらすぐ相談できる窓口を示す。
- 成功・失敗のどちらでも振り返りを行い、良い点を具体的に褒める。



部下は小さな成功体験を積み重ねると、徐々に自信をつけ、チーム全体の成長エンジンになりました。
アプローチ③:成長を振り返り、次のステップへ GO〜!
月に一度くらい
– この1か月で出来るようになったこと
– 次に挑戦すること
を一緒に振り返ると、
「自分は前に進んでいる!」と、
次の仕事にもやる気が湧いてくる。
なぜ振り返る?
- 振り返りで自分の成長ポイントを言葉にすると、学んだことが頭にしっかり定着しやすい。
- 「できた!」という小さな成功体験が積み重なると、自信 がアップしてチャレンジしやすくなる。
- 成長を実感できると、「次も頑張ろう」とモチベーションが続きやすい。
実践ヒント
| やること | 具体例 | コツ |
|---|---|---|
| 月1回 1on1 ミーティング | 1人15分でOK。 「できたこと」 「次にやること」 を3分でメモしてもらう | メモは箇条書きで十分 |
| 小さな前進も具体的に褒める | 「先月より報告が早くなったね!」 | 数字や事実を添えてほめると伝わりやすい |
| 改善点は 「次の目標」として合意 | 「次は資料のまとめ方をもう少しシンプルにしよう」 | できるだけ期限付き・具体的に決める |



小さな進歩でも声に出して認める と、部下は安心して次のチャレンジに踏み出せました!
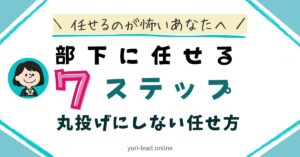
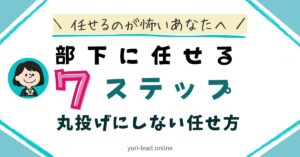
まとめ


この記事の大事なポイントをまとめます。
- 部下が動かない背景は
①目標や役割がぼんやり
②失敗が怖い
③過去に叱られた経験
の三つが多く、まず原因を一緒に探ると対策が立てやすくなる。 - 質問にすぐ答えず「君はどう思う?」と返すだけで考えるクセがつき、自分で答えを出せた体験は行動意欲を底上げする。
- 会議進行や選択肢の決定など小さな権限を段階的に渡し、迷ったら相談できる窓口を示すと責任感が芽生え、自分で動けるスピードが身につく。
- 結果より行動を具体的に褒め、次に直す点は一緒に決めると「やって良かった→もっと試そう」の循環が生まれ、前向きなチャレンジが続く。
- 週1の成功・失敗シェア、役割肩書き付与、月1の振り返りを回すと互いに学び合い責任を持つ文化が定着し、自走チームに変わる。



リーダーのちょっとした工夫で、部下が本気で動くチームに変わります。
今日からぜひ実践してみてくださいね!
↓一人で抱え込みがちな新米リーダーへ
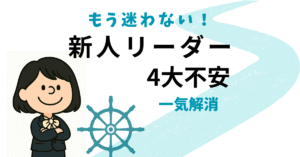
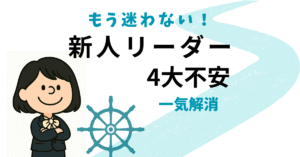
↓責任を抱え込みがちな完璧主義タイプ
↓自分の適性を確かめたい新卒・若手
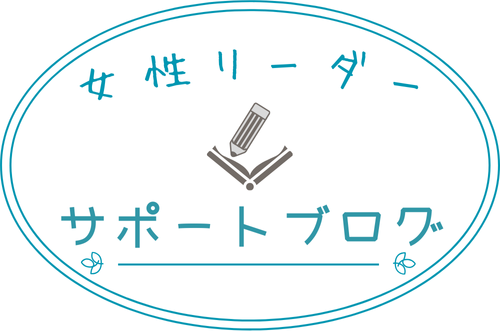
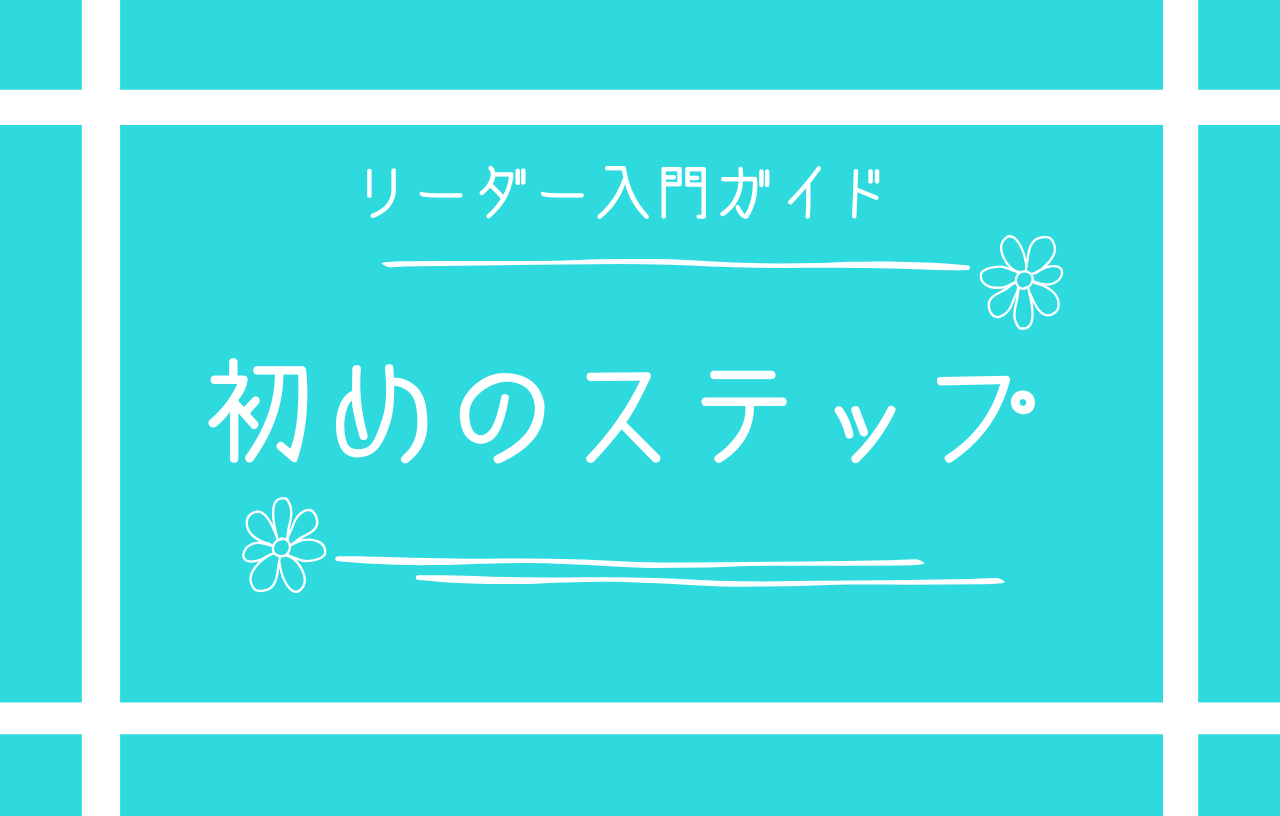
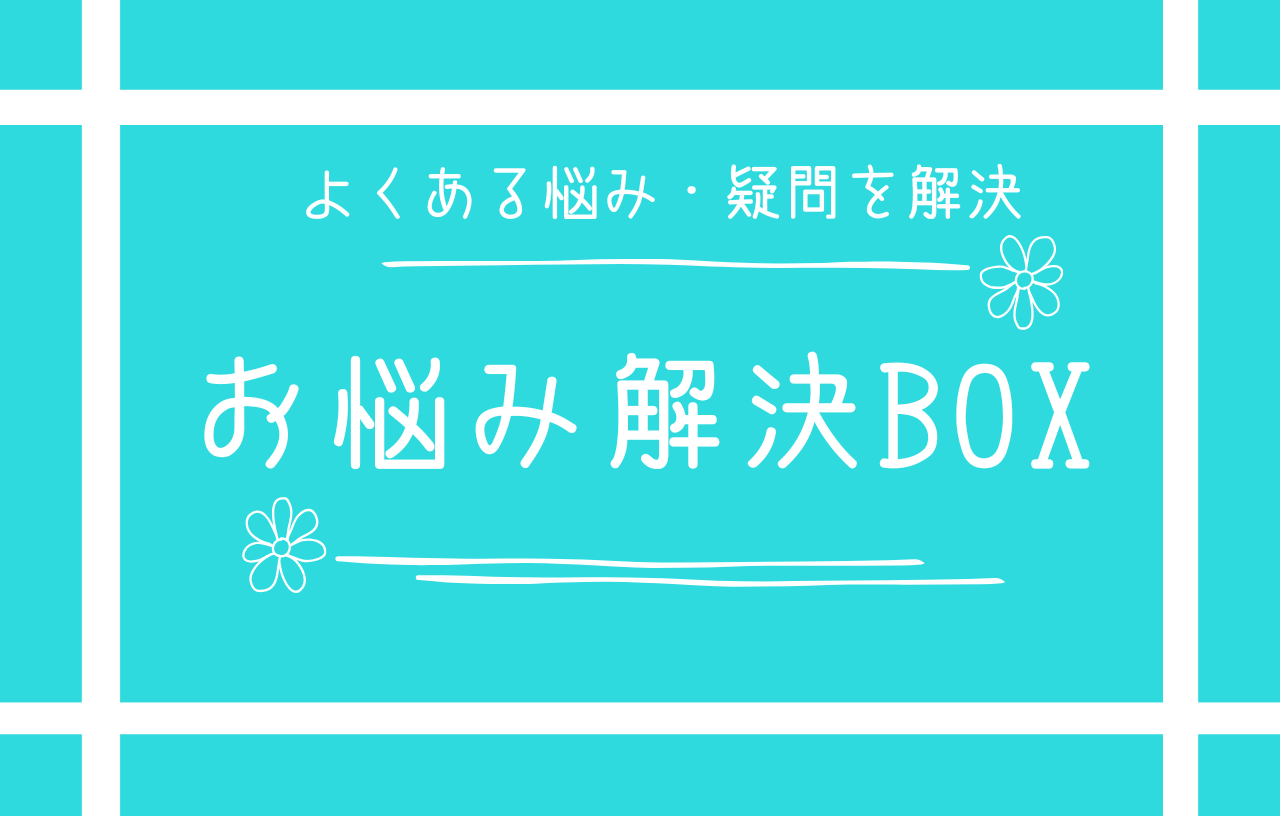
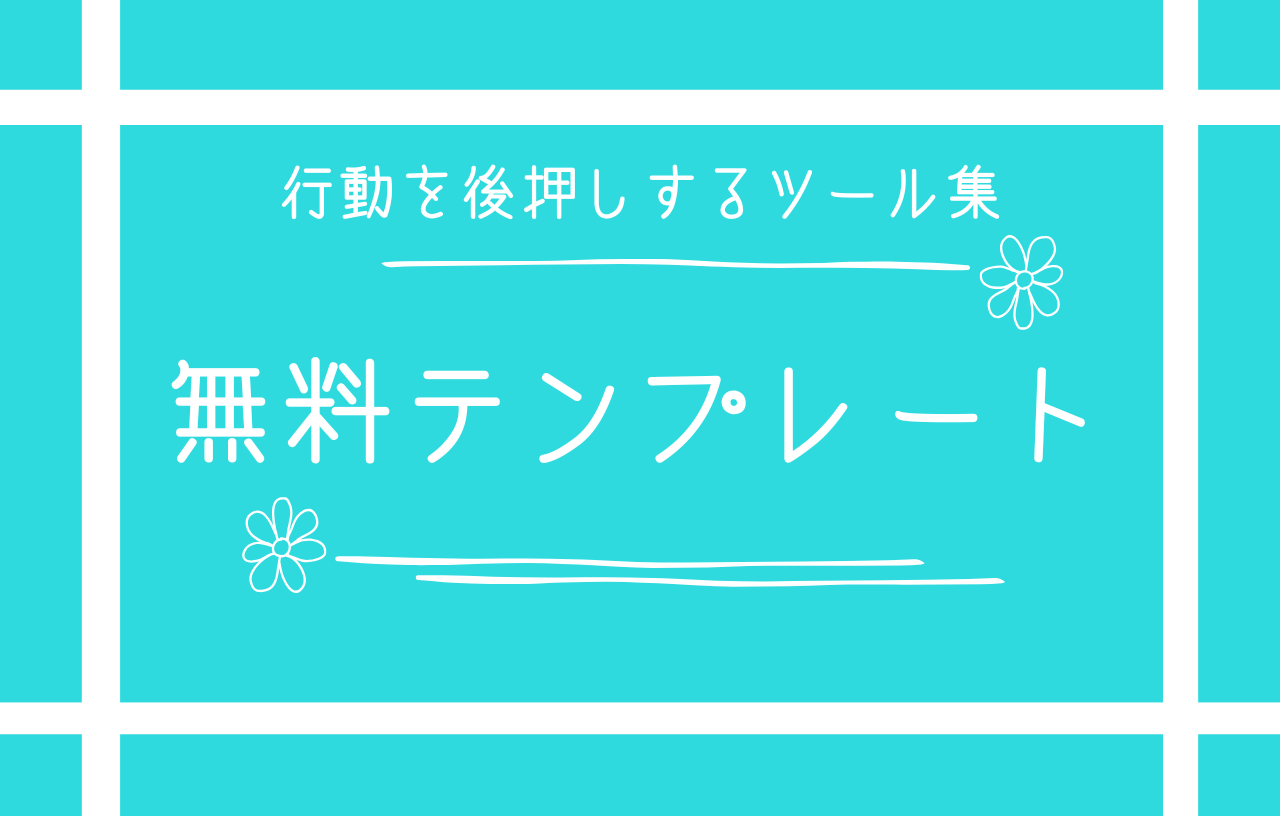
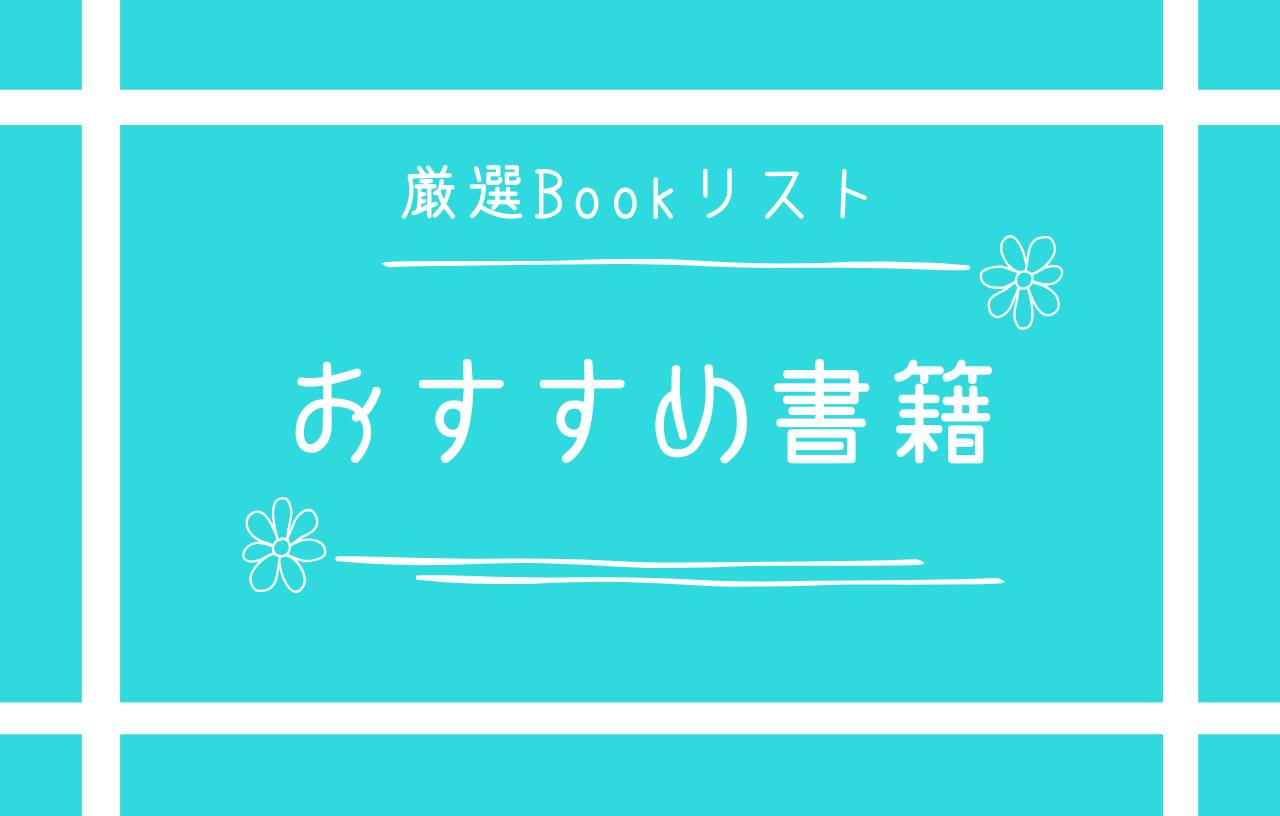
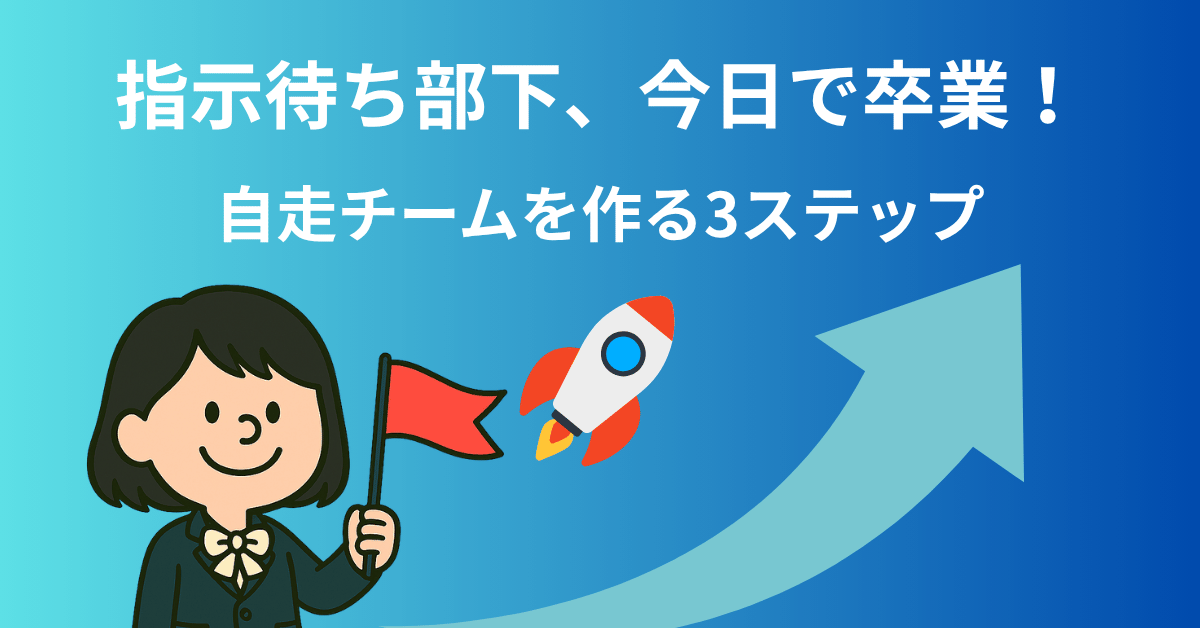

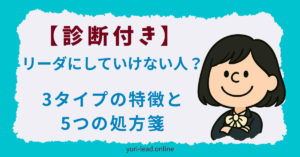
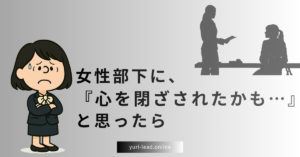


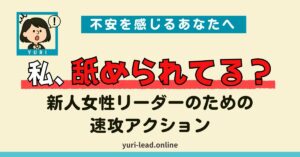
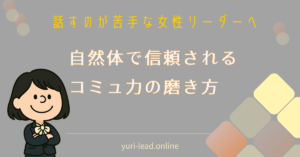
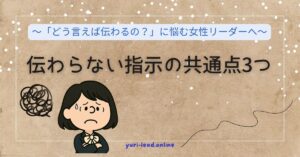
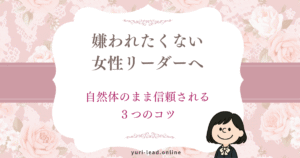
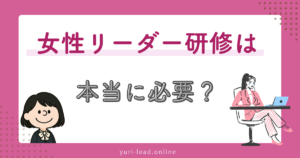
コメント